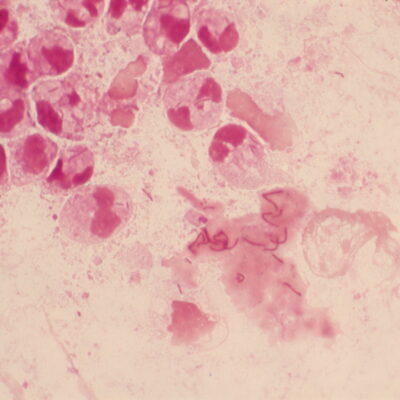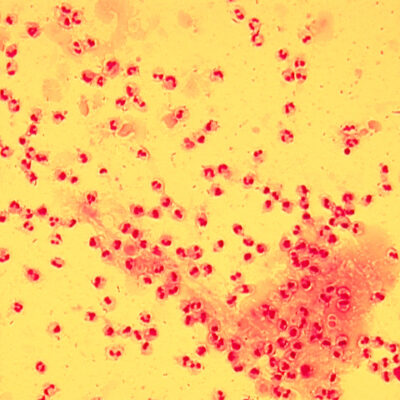- 英文タイトル:Exploration of Trends in Antimicrobial Use and Their Determinants Based on Dispensing Information Collected from Pharmacies throughout Japan: A First Report
- 雑誌名:Antibiotics
- 著者:Yuichi Muraki et al.
- 掲載年月:2022年5月
- URL:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9138112/
- DOI:10.1016 / S0140-6736(21)02724-0
Executive Summary
目的:
抗菌薬の不適正な使用は、薬剤耐性(AMR)の発生に繋がるため、世界的な問題となっており、抗菌薬の使用量を監視することは非常に重要と考えられている。本研究では、薬局で用いることができる新たな抗菌薬使用量(AMU)の指標として、「Defined Daily Doses(DDD)」/「1000処方箋/月(DPM)」の有用性を評価し、日本全国の薬局における抗菌薬使用パターンを明らかにすることを目的とする。
この記事の続きをお読みいただくには、
ログインまたは会員登録が必要です。