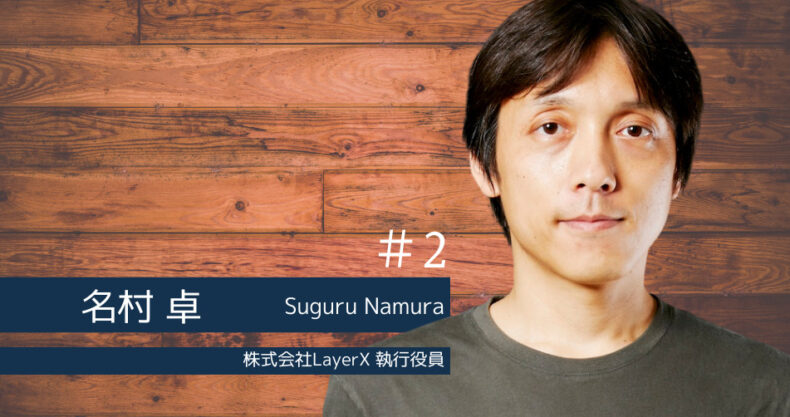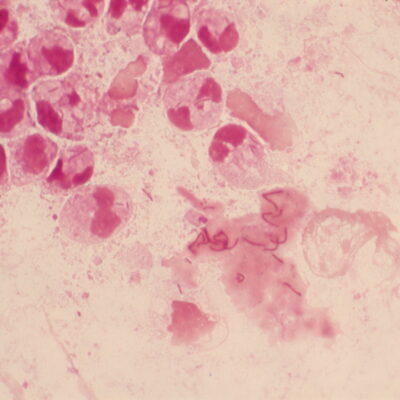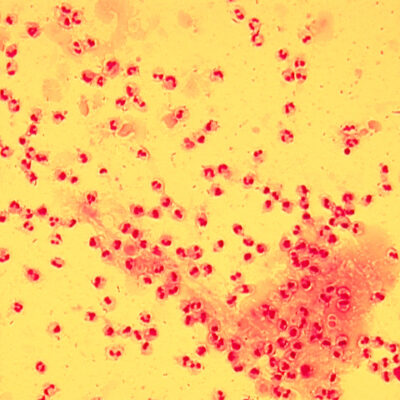(カーブジェン有泉(以下、有泉))アメリカのメルカリに1、2年間ほど勤められていたと伺いましたが、米国でメルカリを開発された際、組織的な観点で日本と違うと感じたところはございますか?
(名村)メルカリは、日本にヘッドクォーターがあり、アメリカはブランチなので、ヘッドクォーターとブランチの心理的、時差的な距離や、単純に遠いためなかなか会えないという物理的な距離を感じました。サイバーエージェント(CA)に勤めていた時代は、同じオフィスの同じフロアで一緒に開発をしていましたが、メルカリに入社してからは、今で言うリモートのような体制の開発業務に切り替わったため、意思決定の仕方や、ディスカッション方法、開発の仕方が日本と非常に違うように感じました。

(有泉)ありがとうございます。また、アメリカのエンドユーザー目線で考えた際、サービスに関して何か日本と違うと感じた点はございますか?
この記事の続きをお読みいただくには、
ログインまたは会員登録が必要です。