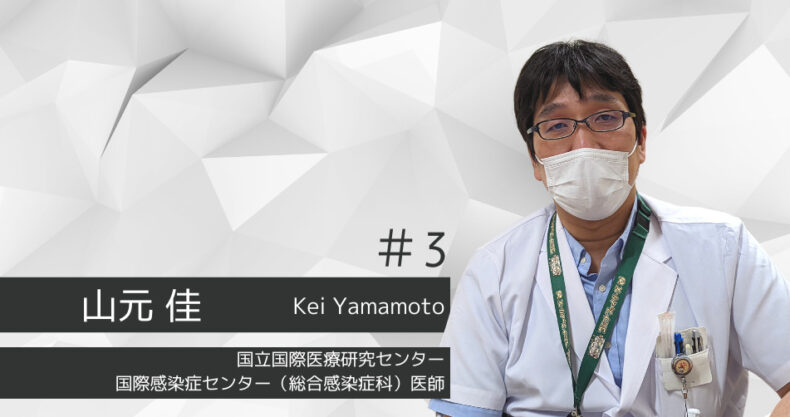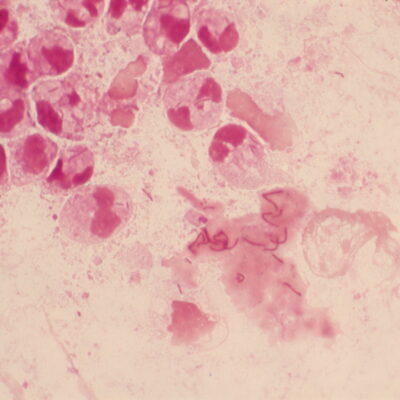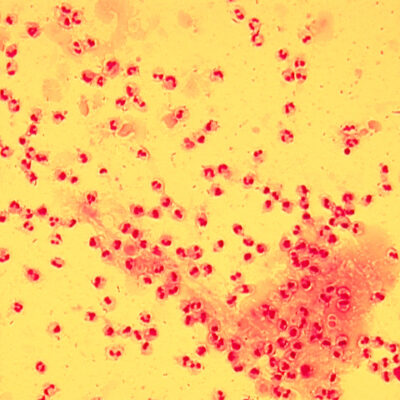(カーブジェン有泉(以下、有泉))最後に、細菌の薬剤耐性(AMR: antimicrobial resistance)問題に関連してお話をお聞かせください。
(カーブジェン中島(以下、中島))AMRの問題の文脈において、厚生労働省や米国のCDC(Centers for Disease Control and Prevention)は抗菌薬の開発のパイプラインが減ってきていると述べていますが、実際に臨床現場では新しい抗菌薬が減ってきていると感じることはありますでしょうか。
(山元)減ってきていると感じます。また、その一端を担っているのは我々なのではないかとも感じます。
(中島)それはどうしてでしょうか。
この記事の続きをお読みいただくには、
ログインまたは会員登録が必要です。