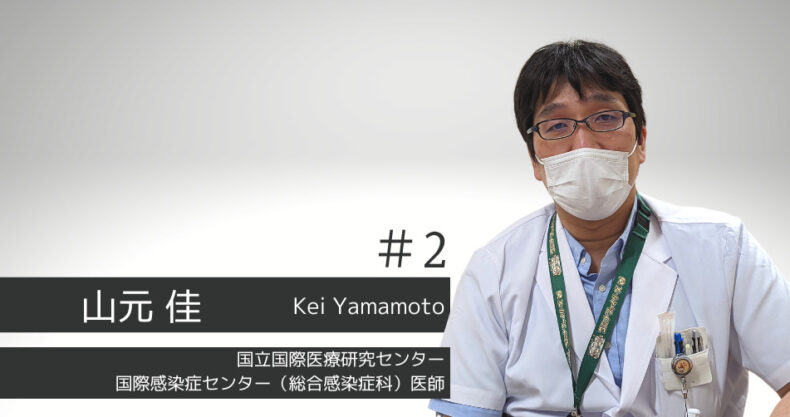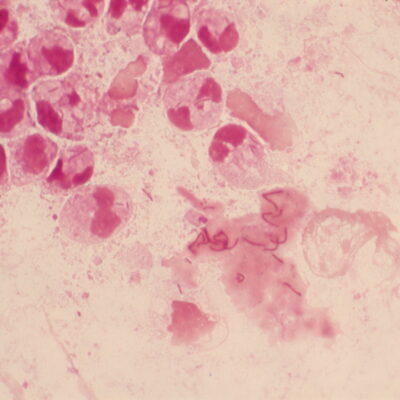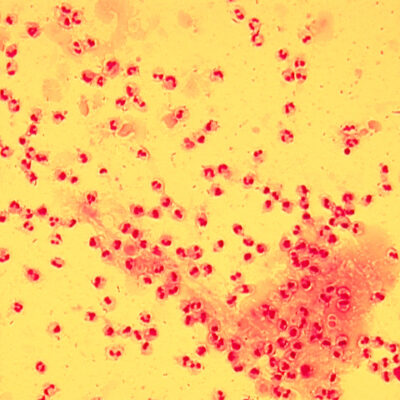(カーブジェン中島(以下、中島))2022年8月現在、山元先生が2011年に国立国際医療研究センター(NCGM)に来られ約11年経ったと思います。COVID-19も然りですが、日本において新興・再興感染症は増えてきているという印象でしょうか。
(山元)そうですね、海外から日本への人の流入が年々増えてきていたこともあり、国内における輸入感染症は増えたと感じることはあります。
(中島)年々地球温暖化が進んできているようにも感じますが、それだけではなくてCOVID-19以前は、インバウンドの旅行者を増やそうという取組を受けて3000万人程増えました。今後それを5000万人、6000万人に増やしていこうという動きの中で、海外との往復量が増えると、いくら水際対策をしっかりとしていても海外からの感染症患者が増える印象はございますでしょうか。
この記事の続きをお読みいただくには、
ログインまたは会員登録が必要です。