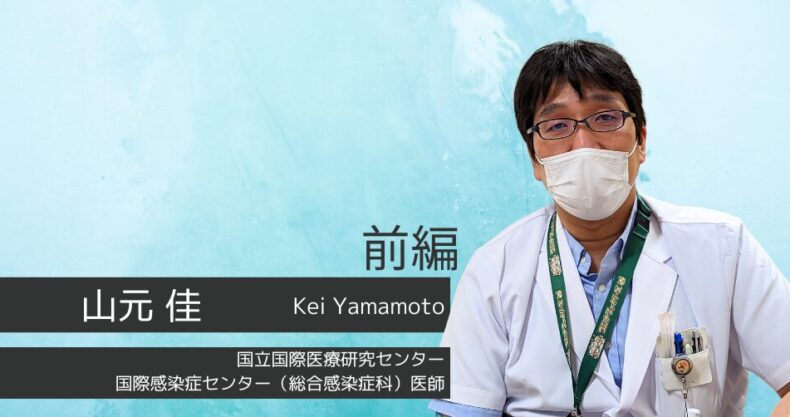1.BiTTE※の開発から医療機器承認までの道のり
(カーブジェン坂田(以下、坂田))本日はお時間をいただき、ありがとうございます。今回は、尿検体を用いた細菌感染症菌種推定支援AIソフトウェア「BiTTE®-Urine※※」が医療機器として承認されたことを受け、その開発に携わられた山元佳先生にお話を伺いたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
(山元)
こちらこそ、よろしくお願いいたします。
(坂田)
まずは、BiTTE®-Urine開発にあたり、なぜ尿検体を対象に選ばれたのかをお聞かせいただけますか。グラム染色の対象としては、喀痰や髄液、血液培養といった検体もありますよね。
(山元)
はい。尿検体を選んだ理由はいくつかありますが、まず、ターゲットとする病原菌を比較的明確に絞ることができる点が大きいです。また、尿検査は医師や看護師を含む多職種が比較的容易に採取できる検査であり、広く検査が実施されているので、臨床アウトカムに直結しやすいと考えました。
一方で、喀痰検体は検査数自体は非常に多いのですが、口腔内の雑菌も混じり、質のよい検体を採取するのが難しく、誤嚥性肺炎も多いので、グラム染色所見で原因菌の推定が難しいことも多いです。
その点、尿検体であれば、得られた結果が診療の判断に直結しやすく、臨床現場での汎用性が高いと考えました。
(坂田)
そうなのですね。単なる菌種の推定にとどまらず、得られた情報がそのまま治療方針の決定に活かされるというのがポイントだったのですね。現場の医師が実際に使うことを見据えて開発されたという背景がよく分かりました。
この記事の続きをお読みいただくには、
ログインまたは会員登録が必要です。